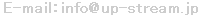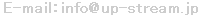「企画概要書」について
企画概要書はゲームの概要を読み手に伝えるために制作します。
書面上の材料で動いているゲームを人に想像させなくてはなりません。
そのために必要なものを企画書として簡潔にまとめます。
無駄があっても、無論、足りないものがあっても「本当に言いたいこと」
は伝わりません。
企画書はゲームを作るために書くのであって、ここでゲームを作るのでは
ありません。
あったほうが良いに決まっていますが、完全なゲーム画像や設定データ
などはあまり必要ではありません。
あくまでイメージの世界でものを動かすのに必要なものがそろっていれば
それでいいのです。
そして、忘れてはならないのが、これは“予算と期間を確保するための書類”
(を想定している)ということです。
|
<企画概要>
「5.発売予定地域とメインターゲット」について
このゲームはどの国の誰を対象に作られるのかを記載します。
ゲームは企画書の読み手を対象に作るわけではありません。
読み手には、対象となっている人の立場でゲームが動いているところを
連想してもらわなくてはなりません。
それが誰なのかをここで明記することで、後述する<企画趣旨>の根拠
を解説しやすくします。
例えば、
販売予定地域:日本および欧米。
メインターゲット:16歳以上の若い男子を中心に。
などある程度幅を限定します。
これが、ゲーム全体のテイストをコントロールする参考になり、また広告
などの情報をどこに発信するべきかの手がかりともなります。
企画を立てるときにターゲットを設定するというのは非常に重要なことの
ひとつなのです。
また、予定販売本数も記載できればなおよいでしょう。
「売る対象」と「売ろうとしている本数」が記載されていることで、
この後で展開される「根拠」に現実味を与えます。
ただし、これはかなりの経験者にのみ可能なことでしょう。
|
<企画趣旨>について
<企画趣旨>は「なぜ」なのかを主に説明します。
「なぜ」この企画を立てたのか、<企画概要>で述べた材料から簡単に説明する。
そして、このゲームの「何がどのように面白いのか」を理論的に解説する。
理論的といっても理屈をこねるのではない。
理にかなった材料を「誰に/いつ/どこで/何を(どのように)する」という
順番にならべ、「なぜ」それが面白いのか読み手にイメージさせる。
選んだ材料に説得力があると、ならべた時点で読み手は面白いことに気がついて
しまう。
くどくど説明するまでもなく楽しさをイメージさせることが出来ればここでは
満点と言える。
例えば、
<企画概要>
ジャンル:3D・対戦型プロレスゲーム
対応ハード:セガ・ドリームキャスト(容量未定)
メモリーバックアップ
ネット通信機能使用
プレイスタイル:最大6人同時対戦プレイ(ネット通信機能でも可能)
販売予定地域:日本及びアメリカ
メインターゲット:13歳以上の男子でプロレスファンを中心に…
と材料をならべたとする。
実現のために必要なことを度外視して話をすると、<企画趣旨>で
「友達とタッグを組んで、顔も知らない国外のプロレスファンとも
対戦が出来る…」などと書くと対象になっている人の立場で想像すると
けっこう楽しげなものに感じると思う。
規模を調査はしていないが、「なぜ」というところでは、
1.プロレスに根強いファンがいること。
2.プロレスを支えてているファン層が主にゲームをする世代の男子で
あること。
3.国内外に周知のプロレスというルール上でわかりやすく多人数プレイ
の対戦格闘ができること。
4.「ネット通信」というプラス要素がファン同士のつながりを利用して
浸透し、大規模なネットワーク構築が期待できること。
などを上げる。
(実現のためにはドリームキャストの処理速度、実名使用のライセンス契約、
通信環境の整備など、パッと考えただけでも問題が多い)
「何を(どのように)する」から「楽しくて」「プレイしてしまう」といった
理にかなったシステムが構築できていれば「面白いゲーム」は完成するでしょう。
|
会社へ出す「企画」について
会社の興味を理解する
売買されるという点でゲームは純粋に商品であって、いち作家の作品とは大きく
性質が異なります。
作るなら作るなりの「勝算」がなくてはなりません。
会社の体制などにもよりますが、そういう意味で企画者は銭勘定が出来ないと
仕事をやっていくことが出来ません。
センス1本で勝負すると言ったところで、会社は“実現できないもの”に興味を
持ってはくれません。
会社の体制に応じた「適度な規模」とそれに見合う「推定利益」を視野に収めた
企画が会社では要求されています。
また、言うまでもなく会社運営の方向性に沿うことも要求されています。
ものの作り方
ものを作るときには逆に「作れない理由」を考えるのが良いでしょう。
「作れない理由」を探すことで「問題」を明確に定義でき、それに対して
「解決策」を考えることで、ものは自ずと成立していきます。
自分の企画が「作れない理由」を抱えている限りは作るべきではありません。
確実に破綻し、帳尻を合わすために苦労するのは目に見えているからです。
「解決策」をプロデューサー(出資者)に委ねる手もあります。
その時は企画概要書に<問題点>の項目をつけます。
プロデューサーの“手”の中で使えるものがあれば、その企画は残していた
「問題」を解決し“GO”がかかります。
もちろん、企画に勝算となる魅力がある時の話です。
|